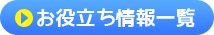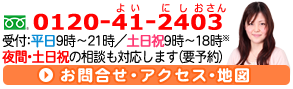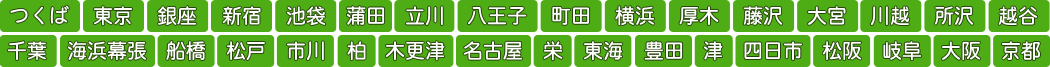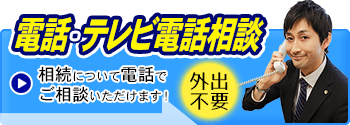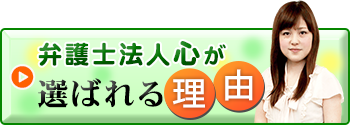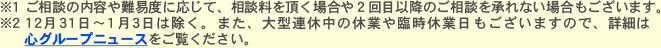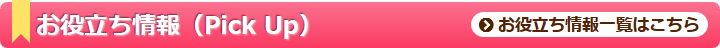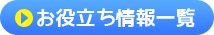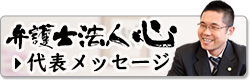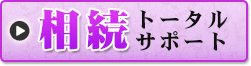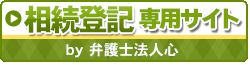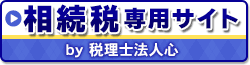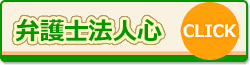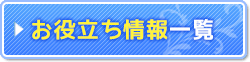不在者財産管理人と遺産分割
1 不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、相続人の中に、行方や所在が不明な人がいる場合、その行方不明者(「不在者」と言います)に代わって、その人の財産を管理する人のことをいいます。
そして、不在者財産管理人を立てるためには、家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立てをする必要があります。
参考リンク:裁判所・不在者財産管理人選任
不在者財産管理人の選任方法としては、基本的に、不在者財産管理人選任申立書と、住民票や不在の事実が分かる客観的資料等の必要書類、収入印紙、郵送切手等を不在者の最後の住所地を管轄する裁判所に提出します。
不在の事実が分かる資料としては、例えば、不在者の住所に送った手紙が、宛先不明で帰ってきたことの書類などがあります。
また、不在者財産管理人を立てる場合は、不在者の親族も不在者の行方を知らないかどうかについて調査する必要があります。
なお、不在者財産管理人には、通常、弁護士や司法書士等の専門家がなることが多いです。
2 不在者財産管理人との遺産分割の内容
不在者財産管理人が裁判所から選ばれたら、その管理人と相続人全員とで、遺産分割協議を行います。
不在者財産管理人は、不在者の利益を守る法的義務があるため、原則として、法律どおりの割合で遺産を取得しなければなりません。
また、不在者にとって不動産は不要なものであるため、金銭の取得を希望するケースが多く、遺産の内容によっては、遺産の分け方でもめることになります。
遺産分割協議がまとまった後は、不在者財産管理人に不在者が受け取った遺産を管理してもらうことになります。
3 帰来時弁済型遺産分割の活用
帰来時弁済型遺産分割とは、相続人が遺産相当額のお金を預かっておき、不在者が帰ってきた時にそのお金を渡すといった分割方法です。
そのため、帰来時弁済型の遺産分割が成立した場合、不在者財産管理人の仕事は終了します。
この帰来時弁済型遺産分割という方法は、遺産の額が少額の場合に認められるものなので、遺産の額が高額である場合にはこの手続きは使えません。
遺産分割調停・審判の管轄 相続人が認知症の場合の遺産分割方法
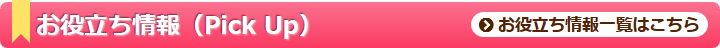
行方不明の相続人がいる場合の遺産分割協議
1 行方不明者がいると遺産分割ができない!
遺産分割は相続人全員で協議して行う必要があるため、相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割ができません。
遺産分割を行う際に不在者財産管理人を立てるか、または、長年に渡って行方がわからないという場合には、失踪宣告手続きを利用する必要があります。
2 不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、行方不明者(不在者と言います)に変わって、財産を管理する人のことを言います。
不在者財産管理人を立てるためには、家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任の申立てを行う必要があります。
具体的な選任申立ての方法としては、申立書に必要事項を記載し、必要書類と一緒に家庭裁判所に提出します。
必要書類としては、不在者の住民票(戸籍の付票)、行方不明の事実が分かる客観的な資料、印紙、切手などがあります。
3 不在者財産管理人と遺産分割協議
不在者財産管理人が選任されれば、管理人と相続人全員とで、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の内容としては、基本的に、法定相続分どおりに分けることになります。
また、不在者財産管理人としては、不動産よりも金銭の方が管理しやすいため、法定相続分相当額の金銭の取得を希望する場合が多いです。
そのため、行方不明者がいると、柔軟な遺産分割協議が難しくなる場合があります。
4 失踪宣告を活用しよう
失踪宣告とは、生死が不明な人に対して、法律上死亡したものとする制度です。
失踪宣告は、生死が7年間わからない人や、戦争、船舶の沈没、震災等の死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年以上明らかでない場合に認められます。
この失踪宣告の制度についても、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
5 失踪宣告後の遺産分割
失踪宣告が認められた場合、失踪者に相続人がいれば、失踪者の相続人全員とで遺産分割協議を行います。
失踪者の相続人が複数人いる場合は、協議をする人数が多くなりますが、不在者財産管理人がいる場合と異なり、柔軟な話し合いができる場合があります。