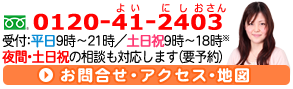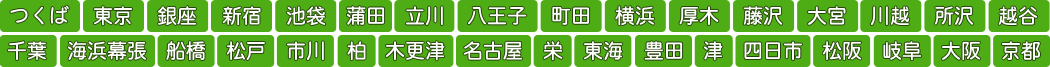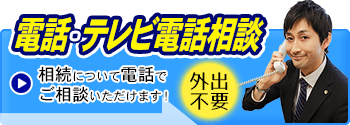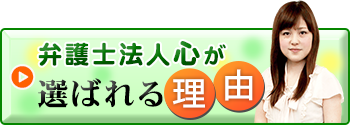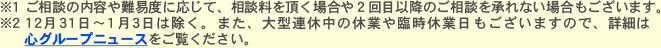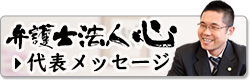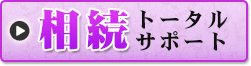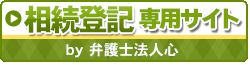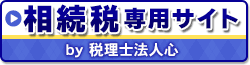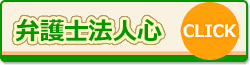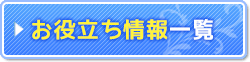遺産分割調停・審判の管轄
1 遺産分割調停・審判には管轄がある
亡くなった方が遺言書を残していなかったり、相続人の間で遺産分割の話し合いができなかったりした場合には、遺産分割調停や審判といった裁判手続きをする必要があります。
この場合、裁判手続きには各裁判所の事件分担の決まりである管轄がありますので、各裁判の事件によって、全国のどこの裁判所に申立てをしなければならないかということが法律で決められています。
参考リンク:裁判所・裁判所の管轄区域
そのため、例えば、ご自分の住んでいる地域に近い家庭裁判所を利用するのが便利であっても、必ずしもその裁判所を利用できるとは限らないということになります。
2 法律上定められた管轄
⑴ 遺産分割調停の場合
遺産分割調停とは、裁判所が中立公正な立場で、遺産分割の方法や内容について話し合いを斡旋する手続きです。
調停については、法律上、相手方の住所地、または、当事者が合意で定める家庭裁判所に管轄があります。
相手方が複数いて、それぞれの住所地を管轄する裁判所が異なる場合には、調停を申し立てる側がその中のいずれか一つの裁判所を選択することができます。
場合によっては、相手方の住所地の裁判所で調停を行うことが当事者全員にとって都合が悪いという場合などもあるでしょうから、当事者全員が合意すれば特定の裁判所で調停手続きを行うこともできます。
⑵ 遺産分割審判の場合
また、遺産分割審判とは、調停で調整がつかなかった場合等に、裁判所が遺産分割の内容を決める手続きです。
審判については、法律上、相続の開始地、または、当事者が合意で定める家庭裁判所に管轄があります。
相続の開始地とは、亡くなった方の最後の住所地をいいます。
3 遠方の裁判所での手続きになった場合
ご自分の住んでいる地域に近い家庭裁判所で調停手続きをできることが便利でしょうから、相手が遠方に住んでいるような場合、相手方の住所地を管轄する裁判所ではなく、できるだけ近くの裁判所に申し立てたいかと思います。
相手方の住所地ではない裁判所に申立書を提出した場合でも、裁判所は、相手方にその裁判所で行うことに同意するかどうかの意向を聞いてくれることがあります。
ただ、調停となるほど遺産分割でもめている場合には、相手方にとって遠方となる裁判所で手続きを進めることに対し、相手方は同意してくれないかと思います。
この場合にも、当事者が裁判所から離れた場所に住んでいる場合には、裁判所が電話会議の方法で手続きを進めることを認めてくれるケースがありますが、手続きの一部については、裁判所に出頭することを求められる場合もあります。